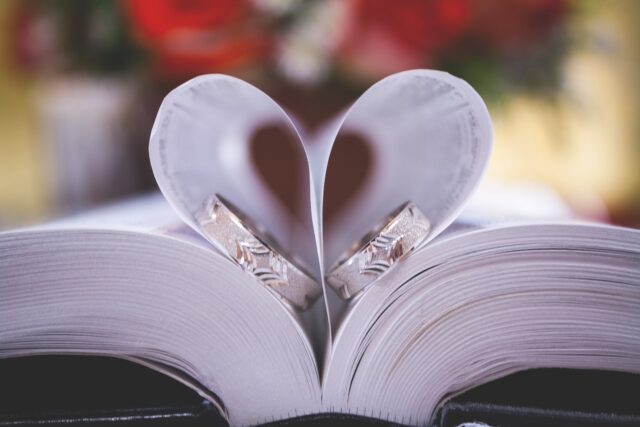金は「安全資産」として長く信頼されてきた存在ですが、実はその価格が大きく下落することもあります。2025年4月初旬も、トランプ政権の関税問題で金相場は一時的に下落しました。
投資家の間では「これからさらに下がるのか?」「買い時なのか?」などの声が高まっています。
本記事では、金の価格が暴落する仕組みや歴史的な背景、現在の経済環境における主な要因を詳しく解説し、今後の見通しなども考察します。
金の価値が暴落することはあるの?

引用元:pixabay
金は長期的に価値を保ちやすい資産とされていますが、短期的には価格が大きく変動することがあります。過去にも、経済状況や市場の動向により金価格が急落した例があります。
例えば、2025年4月には、米国の新たな関税政策や米ドル安により、金価格が一時的に下落しました 。このように、金価格はさまざまな要因に影響を受けるため、常に安定しているわけではありません。
参考:Reuters
安全資産でも下落
金はリスクを避ける資産、いわゆる「安全資産」として知られています。株式市場が不安定なときや、地政学リスクが高まった際には投資マネーが金に流れ込みやすく、その価値が上がる傾向にあります。
しかし、その「安全資産」のイメージとは裏腹に、金価格は短期的に下落することも少なくありません。例えば2025年4月、トランプ関税により急激な円高が進み、金の価格が下がる局面が発生しました。
つまり、「安全資産=不動の価値」ではなく、金もあくまで市場で売買される商品である以上、状況によっては大きく値を下げることがあるのです。
参考:G20控えてベッセント財務長官のドル高支持が響く、経済指標の注目度下がりトランプ節での上げ下げ続く
歴史的にも暴落あり
金価格は過去にも大きな下落を経験しています。
例えば、2024年10月30日に一時1オンス=2,801.8ドルの高値をつけた後、11月14日には2,541.5ドルまで下落し、半月で約9.3%の下落率を記録しました。このような急激な価格変動は、金が安全資産であっても市場の動向や経済指標、政策の影響を受けやすいことを示しています 。
一時的な調整も多い
金価格の「下落」といっても、それが常に暴落につながるとは限りません。多くの場合、一時的な調整に過ぎないこともあります。
特に金は長期投資の対象として見られることが多く、短期的な値動きに過剰に反応して売却してしまうと、本来得られるはずのリターンを逃すこともあります。
2025年4月現在も、金価格は数週間で5~10%下落する場面がありましたが、これは過去数カ月間の高騰に対する反動であり、必ずしも「暴落」とは言い切れません。投資家にとって大切なのは、短期の値動きではなく、長期的な視点で金を捉えることです。
参考:金価格予測今日2025年4月24日国内および世界の金価格に新たな波が
金が暴落した主な原因
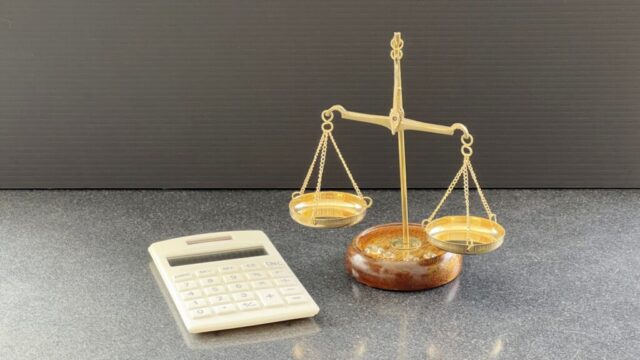
引用元:pixabay
現在、なぜ金は暴落してしまったのでしょうか。その主な理由を見ていきましょう。
供給増で価格下落
金の供給が増えれば、価格が下がるのは市場原理として当然です。例えば、新興国で大規模な金鉱が発見されたり、再利用(スクラップ)金の回収量が急増したりすると、需給バランスが崩れて価格は下落します。
2020年代に入り、再生金のリサイクル技術が向上し、宝飾品や電子機器から取り出される金の供給が拡大しています。このように、「掘る金」だけでなく「回収する金」が増えたことで市場への流通量が上がり、価格下落の一因になっているのです。
需要減が影響
一方で、金に対する需要が減れば、当然価格にも下落圧力がかかります。特に、世界経済が安定し、株式や不動産などのリスク資産への投資が活発になると、安全資産である金への魅力は相対的に薄れます。
さらに、2025年にはデジタル資産(仮想通貨)への信頼が回復傾向にあり、一部の投資家は金ではなくビットコインなどに資金を移しつつあるのが現状です。このような「金離れ」が広がると、需要が減少し、価格下落を招く要因となります。
他資産への資金移動
投資家の資金が金から株式や債券、不動産などに移動することも、金価格が下がる大きな理由の一つです。特に、米国の経済指標が好調で株価が上昇する局面では、金を売って株式に乗り換える動きが強まります。
金は利息を生まない資産であるため、利回りの良い他の資産が魅力的に映るのです。2025年4月も、米国の金利上昇を背景に米ドルと米株への資金流入が進み、金から資金が抜ける傾向が見られました。
為替の変動による影響
金は世界共通で米ドル建てで取引されているため、為替相場、とくに「ドル高・ドル安」が金価格に大きく影響します。米ドルが強くなると、他国通貨建てで見ると金の価格が割高になり、海外の投資家が金の購入を控えるため、結果的に金価格が下落します。
日本では円安が進むと、国内の金価格は上がる傾向にありますが、為替の影響で実際の市場価格と乖離することもあるため注意が必要です。
政策金利の上昇による圧力
2025年も続く米国の金利引き上げ政策は、金価格にとって逆風となっています。金は利息や配当を生まないため、政策金利が高い状態では相対的に投資対象としての魅力が薄れます。
その結果、金を保有しているコストが割に合わないと判断され、売却されやすくなるのです。米連邦準備制度理事会(FRB)がインフレ対策として利上げを継続する限り、この圧力は続くと見られています。
金の暴落で起きる市場への影響

引用元:pixabay
金が暴落すると市場ではどのような影響が起きるのか、以下で見ていきましょう。
ETF売却が進む
金価格が下落すると、投資信託やETF(上場投資信託)に組み込まれている金も売られる傾向にあります。ETFは機関投資家だけでなく個人投資家にも人気のある投資商品であるため、価格が下がると連鎖的に売却が進み、相場の下落に拍車をかけることがあるのです。
特に近年は、金ETFを短期売買目的で保有している投資家も増えているため、ボラティリティの高まりとともに一気に売りが加速するリスクがあります。
金融市場も連動下落
金の価格が大きく下がると、他の金融市場にも悪影響を及ぼします。特に「金=安全資産」のイメージが根強いため、その金が売られているという事実自体が市場全体の不安心理を刺激し、株式や債券市場にも売りが波及するのです。
実際に2020年3月のコロナショック時には、金価格が一時急落し、同時にNYダウや日経平均も大幅下落となりました。投資家が「キャッシュ化」を優先し、すべての資産を手放すようなパニック売りが起きることで、金を含めたあらゆる市場が共倒れ状態になることもあります。
参考:コロナショックで株価が暴落する中、金相場も7年来の下げ幅に
投資家心理が悪化
金の急落は「安全資産すら信じられない」という心理を投資家にもたらし、市場全体のセンチメントを冷やします。特に、退職後の資産運用や長期保有を目的として金を持っている層にとっては、価格の下落が将来の不安に直結するため、その影響は深刻です。
また、他の資産に対しても「次はどれが下がるのか」などの警戒感が強まり、全体的なリスクオフの姿勢が広がります。結果として市場の取引量が減少し、ボラティリティが高まる要因にもなります。
リスク資産への回帰加速
一見すると逆説的ですが、金の価格が大きく下がることで、投資家が株式などのリスク資産へと資金を移す動きが強まる場合もあります。特に、金価格の下落が「インフレ懸念の後退」や「金利の正常化」などのポジティブな経済指標によって引き起こされている場合には、その分株式市場への信頼が高まり、資金が流入する構図が生まれるのです。
つまり、金暴落の背景が「景気回復」を伴うものであれば、投資マネーはより高い利回りを求めて株や不動産に流れやすくなります。
コモディティ市場全体への波及
金が下がると、同じくコモディティに分類される銀・プラチナ・パラジウムなどの貴金属、さらには原油や天然ガスなどのエネルギー資源にも波及効果が及びます。これは、コモディティ市場が全体として連動しやすい性質を持っているためです。
金の価格が下がることで他の資源価格も「リスクあり」と判断されやすくなってしまいます。
また、コモディティ関連のファンドや指数連動型ETFでは金が一定比率を占めることが多く、その下落に伴ってポートフォリオ全体のバランスが崩れ、売りが広がるケースもあります。
金の暴落に対する各国中央銀行の対応

引用元:pixabay
金が暴落したことに対し、各国の中央銀行ではどのような対応がされたのか見ていきましょう。
金の買い支えを実施
金価格が下落傾向にあるとき、各国の中央銀行は「買い支え」に動くことがあります。特にロシアや中国、インドなどは、自国通貨の価値安定や対米リスクヘッジのために、戦略的に金準備を増やしてきました。
2024年~2025年にかけても、金価格が下落すると中国人民銀行やトルコ中央銀行が積極的に金を買い増す動きが見られました。こうした動きは金市場にとって一定の下支えとなり、投資家心理の悪化を防ぐ役割も果たしています。
金融緩和で市場が安定しつつある
金暴落後、中央銀行が取るもう一つの重要な対策が「金融緩和」です。金の価格下落が金融市場全体の混乱につながる場合、中央銀行は金利の引き下げや資産買い入れなどを通して市場に流動性を供給し、安心感を与えます。
例えば2020年のコロナショックでは、FRB(米連邦準備制度理事会)が即座にゼロ金利政策を導入し、市場の不安を鎮めました。2025年現在も、主要国の中央銀行は市場の過度な動揺を抑えるために、柔軟な対応姿勢を見せています。
参考:FRBは異例の金融緩和策を維持(2020年4月)FRBの緩和は長期化、経済活動の再開を待つ
外貨準備でリスク分散
各国の中央銀行は、外貨準備の一部として金を保有しています。金価格の急落は一時的な損失を生みますが、長期的には「通貨リスク」や「信用リスク」を避けるための資産分散先として、依然として重要視されています。
特に、米ドル一極集中のリスクを回避するため、中国やインドは金の保有比率を高めているのが特徴です。
金の暴落と今後の価格動向の見通し

引用元:pixabay
今後金の価格はどうなっていくのか不安を感じる方も多いでしょう。ここからは、今後の価格動向の見通しについて解説していきます。
一時的な反発期待
金価格が急落した際には、一時的な反発(リバウンド)を狙った買いが入りやすくなります。これは短期的な価格調整や過剰反応に対する修正の動きともいえます。
過去にも米国の金利発表や地政学リスクに過剰に反応して一時的に下げた金相場が、その後数日~数週間で一定の水準まで戻した事例は少なくありません。短期投資家にとってはこうしたタイミングが「拾い場」となり得ることから、短期的には反発の余地があると見る向きも多いのが現状です。
ただし、継続的な上昇トレンドに転じるかどうかは別問題で、慎重な見極めが求められます。
中長期は不透明
金の価格動向は、中長期的には不透明感が強まっています。米国の金利政策や世界経済の減速懸念、ドルの強さなどが複雑に絡み合い、明確な方向性をつかみにくい状況が続いています。
特に2025年現在、米FRBの利下げ観測が弱まったことや、中国経済の成長鈍化が世界の投資マネーに影響を与えており、金相場の重しとなっているのです。
さらに、暗号資産やAI関連株などの新たな投資対象が台頭する中で、金の立ち位置そのものが変化しつつあるのも事実です。そのため、「金はインフレヘッジになるから買っておけば安心」などの従来の価値観だけでは、今後の相場を見通すのは難しいでしょう。
需給が鍵を握る
金価格の行方を左右する大きな要素の一つが、需要と供給のバランスです。特に中央銀行による金の買い増しや、宝飾品需要の動向、産出国における生産状況などが価格形成に大きな影響を与えます。
例えば中国やインドでは、結婚シーズンや贈答文化により金の需要が一定の周期で高まる傾向があります。また、金鉱山の生産コストが上昇していることも、供給の面で価格を支える材料の一つです。
加えて、環境配慮や労働問題から新規採掘に制限がかかるケースも増えており、今後は「簡単に供給が増えない」点も見逃せません。このように、ファンダメンタルズ面から見ると、金価格が中長期的に下支えされる可能性も十分に考えられます。
金の売却は今はやめておいた方がいい?

引用元:pixabay
金の価格が下落している局面で、手元の金をすぐに手放すべきかどうか悩む方も多いでしょう。しかし結論から言えば、「いま慌てて売る必要はない」という見方が有力です。
なぜなら、暴落局面はあくまで一時的な調整である場合が多く、過去にも数か月~1年単位で価格が戻ってきた事例が繰り返されているからです。
例えば、2020年初頭のコロナショック時には一時的に金価格が急落しましたが、その後は各国の金融緩和政策により急速に回復し、過去最高値を更新しました。つまり、現在の下落も冷静に見れば「一時的な波」であり、慌てて売却することで逆に損失を確定させてしまう可能性があります。
もちろん、今後も価格が下がるリスクはゼロではありませんが、売却を急ぐよりは、しばらく様子を見る選択肢も十分に価値があります。どうしても売却を考える場合は、信頼できる業者で複数の査定を受け、納得のいく価格で手放すことが大切です。
まとめ
金の暴落は一時的なショックを市場にもたらし、ETFの売却加速や他の金融市場への波及など、さまざまな影響を引き起こします。しかし、短期的には反発の兆しが見られることも多く、中長期的な展望については今後の需給バランスや各国の金融政策に大きく左右される点に注意が必要です。
また、金の売却を検討する際には、「今は本当に売り時なのか?」を冷静に見極めることが何より重要です。金を売るにしても、焦らず、信頼できる業者を選ぶことが大切です。
ブランドガーデン株式会社では、これまでの経験を活かし、お客様の大切な資産を丁寧に査定いたします。金の売却を迷っている方は、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、お客様の状況に合わせた最適なアドバイスをご提供いたします。