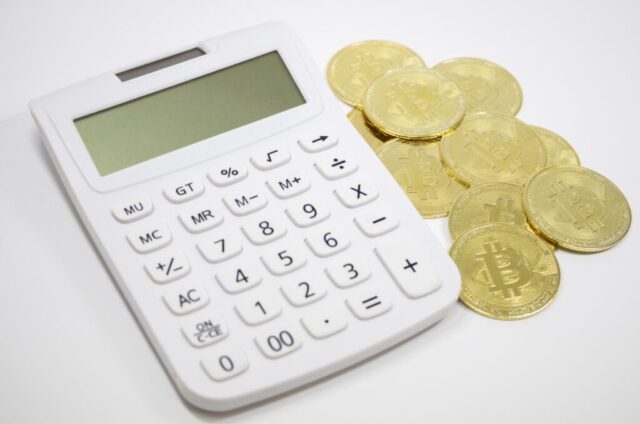
金の売却を考えている方にとって、税金の問題は避けて通れません。本記事では、金の売却に伴う税金の基本から、具体的な所得区分、非課税条件、そして節税対策まで詳しく解説します。
金売却時の所得区分や課税の発生条件、さらには確定申告が必要なケースについても解説するので、税金対策をしっかりと行いたい方はぜひお読みください。
金の売却における税金とは

引用元:pixabay
まずは、金の売却における税金に関して解説します。
利益に対して課税される
金を売却して利益が出た場合、その利益に対して税金が課されることがあります。課税対象となるのは、売却価格から購入価格や売却時の手数料などを差し引いた「売却益」です。
つまり、金を売却して得た金額すべてではなく、実際の利益部分に対して課税されます。この売却益が一定の条件を満たすと、所得税の課税対象となります。
50万円を超えると課税対象になる
金を売却して得た利益(売却益)は、原則として「譲渡所得」として課税対象になります。ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられており、年間の売却益が50万円以下であれば課税されません。
例えば、金を売却して得た利益が30万円であれば、特別控除の範囲内となり、税金は発生しません。ただし、同一年内に複数回の売却を行った場合は、合算して50万円を超えるかどうかを判断する必要があります。
参考:No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
30万円以下の宝飾品は非課税となる
金製のジュエリーや宝飾品などの「生活用動産」を売却した場合、1点または1組の売却価格が30万円以下であれば、非課税となります。これは、日常生活で使用される動産の売却益に関しては課税しないという税法上の取り扱いによるものです。
ただし、売却価格が30万円を超える場合や、営利目的での売却と判断される場合は課税対象となるため、注意が必要です。
販売損なら税金は不要
金を売却して損失が出た場合(購入価格よりも売却価格が低い場合)、その損失に対して税金が課されることはありません。ただし、譲渡所得に該当する他の資産(例えば、他の金製品や株式など)の売却益がある場合は、同一年内であれば損益通算が可能です。
金の売却による損失を他の譲渡所得の利益と相殺することで、課税所得を減らせます。
金の売却で税金が発生する所得区分

引用元:pixabay
金の売却で得た利益には、すべてのケースで税金が発生するわけではありません。ここからは、金の売却で税金が発生する所得区分についてご紹介します。
通常は譲渡所得になる
個人が保有していた金を売却し、営利目的でない場合、得られた利益は「譲渡所得」として扱われます。譲渡所得は、売却益から年間50万円の特別控除を差し引いた額が課税対象となります。
さらに、金の保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、課税対象額が半分に軽減されます。
一方、保有期間が5年以内の場合は「短期譲渡所得」となり、軽減措置は適用されません。このように、保有期間によって課税額が異なるため、売却時には保有期間を確認することが重要です。
参考:No.1460 譲渡所得(土地、建物及び株式等以外の資産を譲渡したとき)
営利性があれば雑所得になる
個人が営利目的で継続的に金の売買を行っている場合、得られた利益は「雑所得」として扱われます。雑所得は、総収入金額から必要経費を差し引いた額が課税対象となり、他の所得と合算して総合課税されます。
また、金投資口座や金貯蓄口座などを利用して得た利益も、実態が金融取引に近いため、雑所得に分類されることがあります。
事業的なら事業所得になる
金の売買を事業として行っている場合、得られた利益は「事業所得」として扱われます。事業所得は、事業による総収入金額から必要経費を差し引いた額が課税対象となり、他の所得と合算して総合課税されます。
また、事業所得の場合、青色申告を行うことで、損失の繰越控除や特別控除などの税制上の優遇措置を受けることが可能です。
雑所得と事業所得の違い
雑所得と事業所得の違いは、主に取引の規模や継続性、営利性などにあります。一般的に、副業として金の売買を行っている場合は雑所得、本業として金の売買を行っている場合は事業所得に分類されます。
また、事業所得は青色申告を行うことで、損失の繰越控除や特別控除などの税制上の優遇措置を受けることが可能です。
金投資口座の利益は源泉分離課税対象
金投資口座や金貯蓄口座などを利用して得た利益は、金融類似商品として扱われます。
基本的に、一律20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉分離課税されます。
この場合、源泉徴収によって課税が完了するため、原則として確定申告は不要です。ただし、他の所得との合算や損益通算はできないため、注意が必要です。
参考:株式・配当・利子と税
金を売却する際の税金に関する注意点

引用元:pixabay
金を売却する際は、税金に関していくつかの注意点があります。以下で詳しく見ていきましょう。
継続売却があると雑所得・事業所得化するリスク
金の売却が継続的かつ営利目的で行われていると判断された場合、所得区分が「譲渡所得」ではなく「雑所得」や「事業所得」として扱われる可能性があります。
雑所得や事業所得に分類されると、他の所得と合算して総合課税されるため、税負担が増加する可能性があります。
特に、副業として金の売買を頻繁に行っている場合は、税務署から事業所得と認定されるリスクがあるため、注意が必要です。
相続・贈与の場合も取得者次第で税負担が変動する
金を相続または贈与によって取得した場合、相続税や贈与税の課税対象となることがあります。相続税は、相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に課税されます。
一方、贈与税は、年間110万円を超える贈与を受けた場合に課税されるのが基本です。
また、相続や贈与で取得した金を売却した場合、その売却益に対する課税は、取得者が金をどのように取得したかによって変動します。
例えば、相続で取得した金を売却した場合、被相続人の取得価格や保有期間を引き継ぐため、課税額が変わる可能性があります。
金の売却益にかかる税金の計算方法
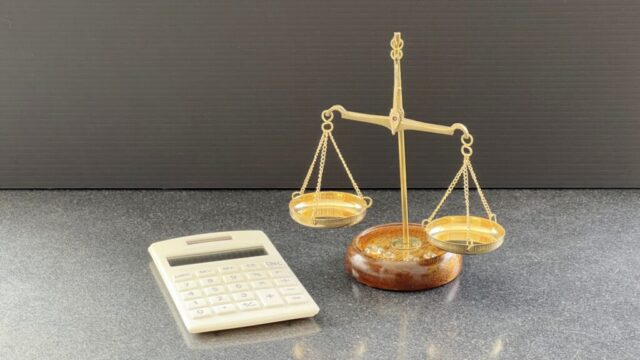
引用元:pixabay
金の売却益にかかる税金は自分でも計算できます。どのくらいの税金がかかるのか、事前に把握するためにも、以下の計算方法を理解しておきましょう。
特別控除で課税額が減る
譲渡所得には、年間50万円の特別控除が適用されます。この特別控除は、同一年内のすべての譲渡所得に対して合算して適用されます。
例えば、金の売却益が30万円、他の資産の売却益が25万円であった場合、合計55万円から特別控除の50万円を差し引いた5万円が課税対象です。
上記のように、特別控除を適用すると、課税額を減らすことが可能です。
取得費が不明なら5%計算
金の購入価格(取得費)が不明な場合、税務上は「概算取得費」として、売却額の5%を取得費として計算することになります。例えば、100万円で金を売却した場合、取得費は5万円とみなされ、95万円が譲渡益として課税対象となるのです。
上記の計算方法は、あくまで取得費の証明ができない場合の暫定措置であり、実際の購入価格がもっと高かった場合でも、証明書類がないと認められません。
そのため、金を購入した際の領収書や証明書、取引履歴などは、将来の売却を見越して必ず保管しておくことが重要です。
また、取得費を証明できれば、その分課税対象となる利益を減らせるため、納税額も抑えられます。過去に購入した金であっても、購入記録が残っている可能性があるため、古い書類やデータも一度見直してみるとよいでしょう。
金を売却した際の確定申告の必要性
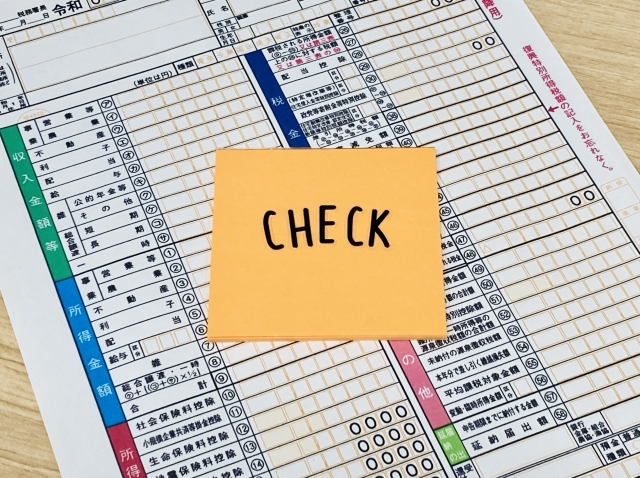
引用元:pixabay
金を売却して利益が発生した場合は、確定申告をする必要があります。しかし、すべてのケースで確定申告が必要になるわけではありません。
以下で、確定申告が必要なケースについて詳しく解説します。
申告が必要なのは売却益が50万円超えの場合
金を売却して得た利益(売却益)は、原則として「譲渡所得」として課税対象になります。ただし、譲渡所得には年間50万円の特別控除が設けられており、年間の売却益が50万円以下であれば課税されません。
例えば、金を売却して得た利益が30万円であれば、特別控除の範囲内となり、税金は発生しません。ただし、同一年内に複数回の売却を行った場合は、合算して50万円を超えるかどうかを判断する必要があります。
20万円以下は申告不要の例外あり
給与所得者(サラリーマンなど)で、給与所得以外の所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。
つまり、金の売却益が年間20万円以下であれば、確定申告を行う必要はありません。
ただし、他の所得と合算して20万円を超える場合や、医療費控除などの適用を受けるために確定申告を行う場合は、金の売却益も申告する必要があります。
e-Taxや郵送でも申告可能
確定申告は、税務署への持参だけでなく、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用したオンライン申告や、郵送による申告も可能です。e-Taxを利用することで、24時間いつでも申告手続きができ、控除証明書などの提出も電子データで行えます。
また、郵送による申告の場合は、申告書類を税務署に郵送することで手続きが完了します。
金の売却で税金を抑えるための節税対策

引用元:pixabay
少しでも、金の売却で得た利益を手元に残したいと思う方も多いでしょう。ここからは、税金を抑えるための節税対策をご紹介します。
長期保有で課税が半減
金の保有期間によって、売却益に対する課税方法が異なります。保有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、課税対象額が半分に軽減されます。
一方、保有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、売却益の全額が課税対象となるのです。そのため、金を売却する際は、保有期間を確認し、税負担を考慮した上で売却時期を検討することが重要です。
取得費の証明を残す
金の購入価格(取得費)を証明する書類を保管しておくことは、譲渡所得の計算でとても重要です。取得費が不明な場合、税務署は取得費を売却価格の5%とみなして課税することがあります。
これは、実際の取得費よりも低く評価される可能性があり、結果として税負担が増加することになります。購入時の領収書や取引明細書などを保管し、取得費を正確に証明できるようにしておきましょう。
分割売却で控除を活用
金の売却益が年間50万円を超える場合、複数年に分けて売却することで、各年の売却益を50万円以下に抑えられ、特別控除を最大限に活用できます。
例えば、100万円の売却益が見込まれる場合、2年に分けて各年50万円ずつ売却することで、課税対象額をゼロにすることが可能です。
ただし、市場価格の変動や売却タイミングによっては、計画通りにいかない場合もあるため、慎重な判断が必要です。
まとめ
金の売却に伴う税金や確定申告に関して正確な知識を持つことは、適切な納税と節税対策に繋がります。特に、売却益が50万円を超える場合や、取得費の証明が困難な場合は、税負担が増加する可能性があるため、注意が必要です。
また、確定申告の方法や期限を把握し、適切な手続きを行うことが重要です。金の売却を検討されている方は、信頼できる買取業者を選び、専門家のアドバイスを受けながら、最適な売却タイミングや方法を見極めましょう。
ブランドガーデン株式会社では、金の買取に関する豊富な実績と専門知識を持つスタッフが、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なご提案をいたします。金の売却をお考えの際は、ぜひブランドガーデン株式会社にご相談ください。














